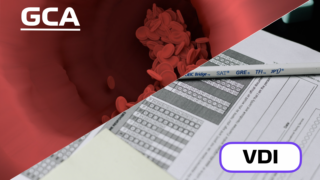 多発血管炎性肉芽腫症
多発血管炎性肉芽腫症 VDI/vasculitis damage index
VDIは非治癒性瘢痕を評価する血管炎の累積ダメージ指標です。3か月以上の臓器障害を対象として評価し、臨床試験で疾患・治療由来の後遺症判定や長期予後推定に有用です。
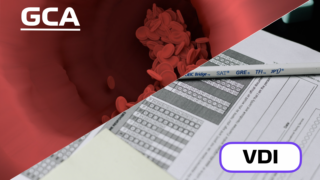 多発血管炎性肉芽腫症
多発血管炎性肉芽腫症 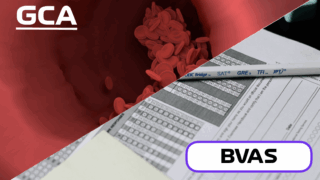 多発血管炎性肉芽腫症
多発血管炎性肉芽腫症 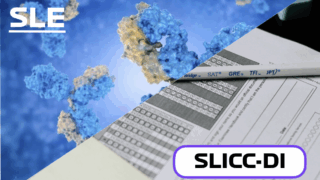 全身性エリテマトーデス
全身性エリテマトーデス 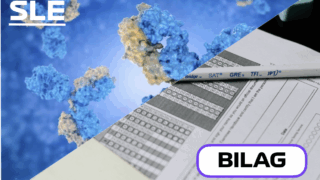 全身性エリテマトーデス
全身性エリテマトーデス 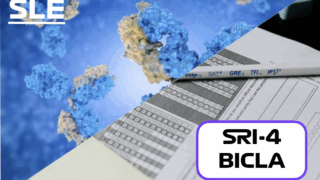 全身性エリテマトーデス
全身性エリテマトーデス  全身性エリテマトーデス
全身性エリテマトーデス 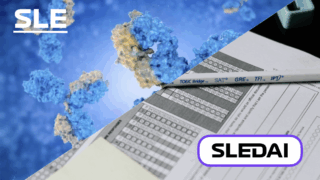 全身性エリテマトーデス
全身性エリテマトーデス 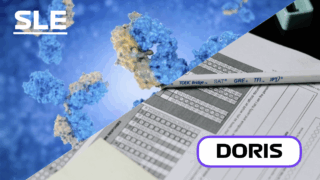 全身性エリテマトーデス
全身性エリテマトーデス 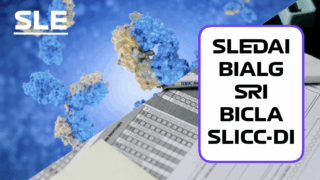 全身性エリテマトーデス
全身性エリテマトーデス 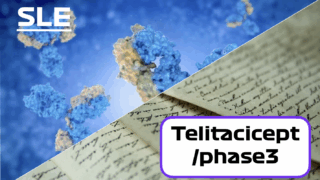 全身性エリテマトーデス
全身性エリテマトーデス